今週の投資判断は以下の通り。
①米国株 NASDAQ100

投資判断:引き続き下落を見込む。買いと同数の空売りは持続的に行い、要所で更なる売り増しと利確を適宜加えることで、証拠金の積み増しを図る。今のところ兆候すら見えないものの、上昇に転じる可能性は最後の最後まで念頭に置く。
②日経平均株価

投資判断:円安は為替介入という大きな節目を迎えている。円安クッションを失った株価は、世界的な地合いに合わせて下落する可能性が高いが、すでにそこそこ下落しており、何もしない。
それぞれの中身は以下の通り。
①NASDAQ100について
チャート的には、6月安値の大台と心理的節目である11,000の大台をほぼ同時に、かつ出来高を伴って割り込んでおり、売り枯れの気配はない。チャートの形状的にも最悪。しかもVIX(31.62)やRSI的にもまだ下落の余力を残している。短期のトレンドラインを割り込み、長期のトレンドライン的には下落余地がある。


SP500もチャート形状は悪い。

ファンダメンタルを見れば、国債の利回りは4%ほどにも達しており、積み立てと空売りの利確以外の株を買う以外の理由が見当たらない状況にある。
英国の国債の騒ぎは一時的な落ち着きを見せているが、これもあくまで一時的であり、国債の買い入れをやめるというのが実行されれば、減税という、ちぐはぐな政策も相まって年金基金まで含めたパニックは再起される可能性が高い。
夜明け前が一番暗いという言葉があるが、こんなに暗いのにまだ一番暗いわけではないという状況。
6月の底値を思い出せば、高騰していたエネルギーが下落に転じ、CPIが大きく上げ、利上げの数値も確定したタイミングで出尽くしの状況から買いが入った。その後のCPIは下落しラリーは持続した。
今回のインフレの主役は住宅(家賃)であり、この「下がりにくい価格」と言われる家賃については、明確な沈静化の気配はない。
可能性の話をすれば景気後退に合わせて下がる期待もできるが、景気は強い。
先週紹介したシーゲル教授の意見や、マンハッタンの家賃が上昇を停止したという情報もあるにはあるが、期待インフレの数値が下がっていない以上、これも持続的なものと言えるかは疑わしい。市場が反応するには、もう少し材料が欲しいところである。
逆に、少しでもインフレ鎮静化の確たる情報が出てくれば、株価は上がり始める気がする。
なお、先週あったような、一時的な謎の急騰は、機関投資家が動かしているのか、自律反発的なものなのか、理由の判断が難しいが、リバースレポによる債権買い(債券利回りが下がり株価が上がる)という説も信ぴょう性がある。
だとすればFRBとしては、株価を下げたいがパニックを起こすほどの急激な下げを避けたい、あるいは、売りで儲けている人間もきっちり仕留めておきたいのか。意図が見えてくれば、この記事でも今後紹介したく、今後も引き続き経過を見ていく。
いずれにしてもきっちり逆指値を入れてとにかく損をしない事を優先して動くことが重要だと考える。
②日経平均株価について
単純に株価が米国の後をついていく可能性は高い。為替の話については、歴史を見れば、日銀の介入が為替相場の折り返し地点となっていることは留意の必要がある。
今回の介入は協調介入でもなく日銀単独であり、政策金利の乖離からも流れは変わらず、勝ち目がないという主流の論調がある。
しかし、為替介入は単独であっても日米政府(両中央銀行)が協議を行った上での行動であることに違いなく、そこで何らかの目論見の一致を見たうえで行っている可能性もある。
日銀の動きを決して軽んじてはいけない。
最後に
こうして考察すればよくわかるが、予測をかなりの精度で当てても、売買判断も同じぐらいの精度と技術がないと利益につながらないことがよくわかる。損切を正しく行い、買う時も売るときも、実はそこに様々なテクニックがあり、それらを正しく実施できて初めて利益が出る。
それらを磨いていくことも重要だが、それでていてシンプルを目指すことが大事なのだろう。

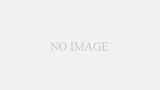
コメント